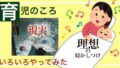出産直後は数時間(2~3時間)毎のミルクタイム……からのゲップ出し。オムツ交換。
自分の身体の面倒をみるのもやっとなのに、赤子の面倒をみないといけない。
夜泣きは、旦那や近所の人の睡眠も邪魔してしまうので気も使う。
我が子は可愛いけれど……ツライ(;_;)。
夜泣きは、親の身心キツキツ生活のオープニングイベントかもしれない(個人差アリ)。
寝かしつけの有効な対策は、やはり『定番』でした
対策①寝かしつけワザに磨きをかける

★優しくゆらゆら抱っこ(定番)
(私の)心臓に、赤子の頭が来るように抱っこすると安心すると聞いたが、我が子の場合その通りだった。
どんな風にすれば、赤子が心地良いのか抱っこ体制や揺らぐリズムを毎回考えてやるうちにワザに磨きがかかってゆく。
★仰向けに寝た自分の上に乗せる。
これも胸の上に赤子の頭が来るように乗せると安心するようだった。
★ベビーカーに乗せる(友人は車でチャイルドシートに乗せて、ドライブすると言っていた)。赤子の様子を見ながらが必須だけど、ちょっと気分を変えるのは、赤子も私も必要に感じた。
抱っこで寝ている赤子をベッドに移す時、成功率を上げる小ワザ👍。
せっかく寝かしつけた赤子を布団に寝かせようとしたら、気づいて起きてしまいギャン泣き…(-“-)という目にあった経験者は結構いると思う。寝かしつけの労力と時間が水の泡…。そのリスクを減らしてくれたのが、この『タオルと一緒に抱っこ&ベッド方法』…というほど、大したことでは無いけど☺。

最初にタオルと一緒に抱っこして、タオルと一緒に布団に寝かせる。
お尻の方から布団に置いて、最後に頭から手を抜くときにタオルに手を滑らせるように抜くと成功率が高い。『シテヤッタリ感』を味わえる。(タオルは赤子にカラまない丁度良いサイズのモノを使おう)
対策②母(私)の身体の回復&赤ちゃんとの生活作りを第一に意識する
★昼と夜のメリハリある生活リズムを、習慣にする。
赤子が外に出ても良い月齢になったら、だんだんと通常の生活を共にするようにした。日中の音や光は赤子に刺激を与え疲れさせ、夜の睡眠につながると保健所の母親学級や検診で聞いたからだと思う。
第2子の娘は、生後2か月から息子の幼稚園生活に付き合って生活していたからか、夜泣きからは早く卒業したと思う。兄の通園送り迎えや、日中の生活音などの刺激に強制的につきあっていたからだろう。新生児からしばらく夜泣きはしたが、長男の事を思うとはやくから夜にたくさん寝てくれた。
★メリハリ生活に耐えられる母の体力回復。そのための休息。無理はしない。
『産後無理はするな』とたくさんの先輩ママさんに言われたが、その通りだと思う。頼れる人やサービスには頼り、体力を回復させるのが何より大切だと思う。そして、無理は禁物。『歳とったら、身体に出るよ。』というのは、なんとなく正解だと、この歳になって思う。

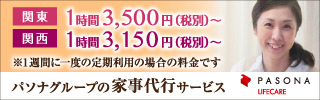
ホヤホヤの赤子に、朝・昼・夜の区別は無い(個人差アリ)
我が家、それなりに大変でした(;_;)。

長男は、『寝ること自体を嫌がる子』だった。
ウトウトとしながらも声を出して泣き、コクっと寝落ちしそうになっては目を開け『アブナイ、アブナイ。寝るとこだった。』とでも言いたそうに、また気合をいれて泣き出す。

その仕草に向かって何度
『眠たいなら、寝ろよ(怒)。』とつぶやいたことか…。
新生児の頃から声量のある子だった。
いくら専業主婦とはいえ(ほぼ)ワンオペ育児で私の身体はキツキツだった。
眠れない毎日…。
常に寝不足。頭が痛い、吐き気がする。
自分が、病気なのか体力が落ちているだけなのかすら分からない。
母乳だったので、薬も安易に飲めない。
あまりに(私の)具合が悪くて、赤ちゃん連れで病院へ行ったら、一目見て点滴を打たれた。
長男を看護婦さんに預けると、チカラ一杯に泣いてしまったので、胸に乗せての点滴。息子は泣き止み、そして眠っていった。
帰宅後、病院での睡眠で充電してイキイキとした息子の遊び相手をして、『イラッ』としたのを覚えている。
そして、夜には魔の寝かしつけタイムがやってくる。
息子の夜泣きは、だんだんと状態が良くなり3歳頃にはずいぶんと楽になったが、小学校に入る頃になってもしばしば悩まされたように記憶している。


赤ちゃんは原因があって泣いている場合(オムツやミルク、発熱など)だけでなく、暇つぶしで泣いている場合もあるらしい。あまりに放置するのは、危険で周りにも気をつかうが、神経質になって『泣かせまい』とするのも、養育者の気が休まらない。期間限定だと思って楽しんで乗り切って♪